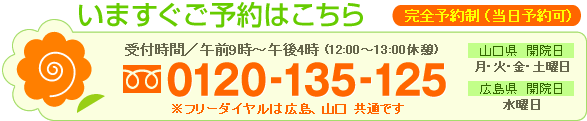TMS理論
TMSとは
TMSとは、「Tension Myositis Syndrome」の頭文字からとった略称で、日本語に訳すと「緊張性筋炎症候群」ということになります。
しかし、「筋炎」といっても筋肉に「炎症」があるという意味ではなく、筋肉内に何らかの変化があるという意味でしかありません。
この理論を開発したジョン・E・サーノ博士は、TMSの定義を「痛みを伴う筋肉の生理的変化」としています。
つまり、腰痛の原因は筋肉組織の血流不足によって起こる酸素欠乏であるという考え方です。
そして血流障害の原因として、精神的ストレス(ネガティブな感情の抑圧)による自律神経の乱れであるとしています。
またTMSは、これまで単独の病気によって生じると考えられていた筋骨格系のさまざまな症状を、ひとつの症候群としてまとめたものです。
たとえば、肩こりと呼ばれている首や肩、背中の痛みをはじめ、腰痛、臀部痛、上肢や下肢の痛みやしびれ、さらに四十肩、五十肩と呼ばれる肩関節の痛み、肘、手首、股関節、膝、足首の痛みまで、これらはすべて共通した原因によるひとつの症候群だと考えます。
これは、サーノ博士の長い臨床経験の中から導かれた結論で、以下の表に示す疾患のすべてをTMSとして取り扱います。
なぜなら、これらの症状はTMS治療プログラムによって、95パーセント前後の確率で改善させられるからです。
椎間板ヘルニア 変形性関節症 尾骨痛
変形性脊椎症 肩関節周囲炎(五十肩) 足底筋膜炎
脊椎分離症 腱板損傷 神経腫(モートン病)
脊椎辷り症 テニス肘 ハムストリング筋断裂
脊柱管狭窄症 手根管症候群 シン・スプリント
脊柱側彎症 線維筋痛 顎関節(TMJ)症候群
滑液包炎 多発性単神経炎 筋肉リウマチ
椎間関節症候群 腰仙移行椎 反復性ストレス障害
潜在性脊椎披裂 筋膜炎 捻挫・疲労など
a:10092 t:1 y:0

 私たちが心をこめて丁寧に施術させていただきます♪常時2人でアットホームな雰囲気でやってますので女性の方も安心してご来院くださいね!
私たちが心をこめて丁寧に施術させていただきます♪常時2人でアットホームな雰囲気でやってますので女性の方も安心してご来院くださいね!